憲法2条の「世襲」には、憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」が前提・制約として掛かっています。
これは、皇室典範2条の「皇長子」に典範1条の「皇統に属する男系の男子」が前提・制約として掛かっていて、ここで規定される「皇長子」に愛子内親王は含まれないことと同じです。
法文の文言を単独で抜き出して辞書的な意味を主張・解釈しても意味はありません。
(辞書的な意味で「皇長子」は天皇の長子の意味だから愛子さまが皇位継承者として法律で規定されている!と主張するいわゆる愛子女帝派も見受けられますが、実際の法運用上は皇室典範2条の「皇長子」として見なされてはおらず、皇位継承順は付与されていません)
法律は前の条文等含めて全体で整合性が取れるように設計されているものとなりますので、法の解釈においては統合的な捉え方が必要で重要となります。
憲法2条は、「象徴」「国民の総意に基く」を満たす(すなわち下位条文・理念とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しない)「世襲」が「皇室典範」に規定され、それに基き皇位継承が執り行われる旨規定されているものとなります。
また憲法2条における「世襲」を捉える上で重要なのは、世襲宮家・世襲親王家(旧宮家の皇族)の即位を前提(有り得る)として規定されているという点です。
日本国憲法の公布は1946年(昭和21年)、施行は1947年(昭和22年)5月3日で、旧宮家の皇籍離脱は1947年(昭和22年)10月14日という時系列です。
日本国憲法も皇室典範も旧宮家皇族が殿下として皇室に存在する形において実際に運用されているもので、時の天皇から数百年離れた皇族が存在してもなんら支障がない規定となっています。
日本国憲法 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
昨今、憲法2条の「世襲」という規定、文言を自己都合で解釈して継承ルールを変えようという論が出ています。
・旧宮家子孫が皇室に入ること、そしていずれかの際に即位することは「世襲」に反するから認められない
・養子は「世襲」に抵触するから認められない
・「世襲」とあるのだから天皇の子の愛子内親王が継ぐべき
などなど。
いずれも失当、全くナンセンス、法的根拠に欠けます。
*
あらためて時系列の整理をすると以下の流れとなります。
1946年 昭和21年11月3日 日本国憲法憲法 公布
1946年 昭和21年11月26日 皇室典範 国会に法案提出
1946年 昭和21年12月24日 皇室典範 国会で議決
1947年 昭和22年1月16日 皇室典範 公布
1947年 昭和22年5月3日 日本国憲法 施行 皇室典範 施行
_※男系男子による天皇の地位が国民の総意に基くものとして施行された
__旧宮家は皇族・宮家であり旧宮家男子は皇位継承順を有していた(7位~32位)
__憲法2条の世襲は旧宮家皇族の即位を含む
1947年 昭和22年10月14日 いわゆる旧宮家(11宮家51名)が皇籍離脱
日本国憲法の施行日である昭和22年5月3日において、旧宮家は皇族・宮家であり、旧宮家男子皇族は皇位継承者として皇位継承順(7位~32位)も有していた経緯ですから、憲法2条における「世襲」概念においては旧宮家の存在、即位可能性が勘案され含まれたものとなります。
そして旧宮家は「世襲親王家」の流れをくむ位置付けであり、時の天皇の近親:血縁の近い順番ではなく、一部の比較近親者を臣籍に降下させつつより遠縁の者を皇族として宮家を存続させ続けて来た「世襲宮家」という位置付けになります。
これは皇統の維持・バックアップという意味で、本統(時の天皇)に近い順番だけでバックアップ体制を作るよりも、一部はより離れた系統でバックアップの備えを用意しておいた方がより安定的になるという深謀遠慮によるものです。
旧宮家の皇族を皇位継承者と位置付け継承順(7位~32位)も割り振った現実において日本国憲法は施行されている経緯ですから、憲法2条における「世襲」概念においては旧宮家の存在、即位可能性が勘案され含まれたものとなります。
よって憲法2条における天皇の世襲においては、五世孫以遠でも良い、大傍系からの即位でも良い、時の天皇から親等が近い順ではなく一部の近親を順番飛ばしした形での即位でも良い、そうした継承も含めて「世襲」の継承であると位置付けらている、規定されているということになります。
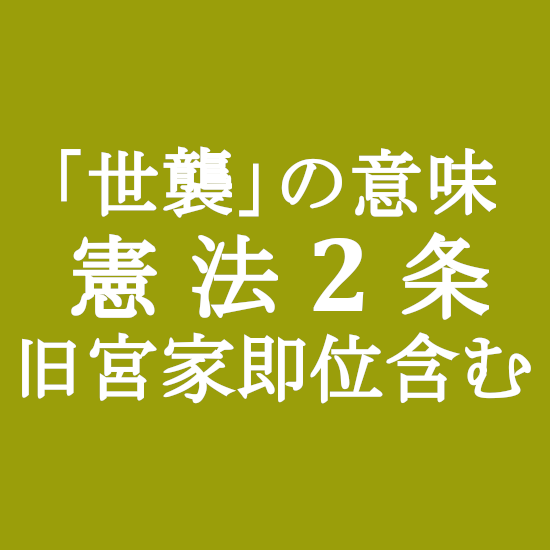
いわゆる「五世孫」以遠でも差し支えない、本統(時の天皇の血筋)から600年以上離れても差し支えなく「世襲」の継承として即位可能との意味合いを持つ憲法条文であり、血筋順を飛ばしてでも近親の男系女子による継承ではなく神武一系の男子(皇統に属する男系男子)による継承を位置付けるという形で「優先捉え」「忌避感覚」が示された規定となっています。
憲法条文、条文の前後関連規定、法律も含めた全体統合性から上記の点を読み解くことが重要となります。現行憲法においては、かなり限定的な形で皇位継承が規定されていることとなります。
つまりは、憲法2条における「世襲」とは神武一系の男子孫による継承ということになります。
(選挙・選抜制や婚姻等による神武一系男子孫以外の者による継承が排除されているという形です。)
そして神武一系の男子孫の中での具体的な世襲のあり方、順位等に関しては「皇室典範」において定められるという位置付けとなります。
こうした憲法解釈、従来の一系継承の捉えの踏襲に関しては過去の国会答弁でも示されているところです。
*
養子に関しては、近親の順を超えた世襲親王家・大傍系の即位も有り得る形で「世襲」が規定されているのですから、神武一系男子孫であるならば養子であっても「世襲」の要件に抵触することはありません。
逆に、神武一系男子孫以外の者に関しては、養子縁組をしたとしても「世襲」には該当しません。
いずれ、憲法2条における「世襲」規定とは別の形で、皇室典範において明示的に養子(神武一系の男子孫であっても)は禁止されていますので、憲法2条「世襲論」ではなく皇室典範論、伝統論=憲法1条「象徴」「国民の総意に基く」の制約の問題として養子禁止の意味に関して確認することが重要と考えます。
皇位の私物化、宮家の私物化、家系伸ばしの私物化となるので排除、禁止されている形です。
皇位の由来根拠は、時の天皇・宮家ではなく、初代神武:建国の和にあるという意味合いから、養子による神武以外の権威付けなどを禁止している形となります。
*
「世襲」だから天皇の娘というのは、まったく法の構造・順序順番を理解しない浅薄であり、皇室典範の規定を議論出来ない者、皇室典範規定を脇に置いて憲法を理由に誤魔化しをしたい者の詐欺的論法と見なさざるを得ません。
国会議員や公務員がこれを言う場合は、憲法99条:憲法尊重擁護義務に反する違憲行為となります。
憲法2条の条文を分かりやすく趣旨の補足すると以下の形になります。
皇位は、(建国の和に由来し原点回帰する神武一系の男子孫による憲法1条の「象徴」「国民の総意に基く」を満たす、すなわち憲法14条「門地差別禁止」等の理念とも根本矛盾しない)世襲のものであつて(神武一系の男子孫以外の継承は認められない)、(神武一系の男子孫の中での継承のあり様、順位等に関しては)国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
天皇の娘が有利になる規定、文言では全くありません。
*
あらためて、憲法1条、4条、5条、14条、99条等を含めた憲法論、憲法における天皇の位置付けを吟味し直すことが重要と考えます。
皇位継承は憲法2条に基き法律事項であって、皇室典範の変更により変えることが出来るという考えもありますが、継承の根幹に関しては憲法1条の規定「象徴」「国民の総意に基く」に制約されます。すなわち下位条文とも根本矛盾しない、憲法14条 門地差別禁止の理念に根本矛盾しないことが求められ、及び2条の「世襲」という規定等によって枠がはめられています。
それらとかけ離れて皇室典範を自由に変えられるものではありません。
【内閣法制局長官 林修三君(昭和34年2月6日 衆・内閣委員会)】
現在の憲法は、もちろん皇位継承のことにつきましては、法律に規定を譲っております。法律である程度のことは書き得る範囲のことがあるはずでございます。しかしこれは憲法第1条が、天皇は日本国の象徴とし、それからその地位が日本国民の総意に基くというこの規定、それから第2条に皇位は世襲のものである。こういう規定と離れて、ただいまの問題を議論することはできないと私は思うわけであります。
…やはりこの象徴たる地位、あるいは国民の総意に基くこの地位というものと相いれない範囲におけるものは、そこに制約があることは当然だと思うわけであります。
憲法の1条とその他の条文(下位条文)との関係性・整合に関して、一般的な上位条文優位はもちろんですが、1条の中身の問題として「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」「日本国民の総意に基く」と規定されている意味は重く、”下位条文・理念とも根本矛盾しない”という捉えが重要となります。
国にとって重要な事柄を憲法条文に規定するのであり、この理念と根本矛盾する天皇・皇位の位置付けならば「象徴」「国民総意」足り得ません。
日本国憲法は非常に高度に作られているものであり、例えば、憲法14条の門地差別禁止の理念と天皇・皇族・皇位継承も根本矛盾しないという前提で捉えるべきで(実際、天皇・皇族・皇位継承における門地的位置付けは非常に限定的)、安易に”飛び地論”などで解釈するのは不相当、憲法の高度さの理解・先人への敬意の不足と捉えます。
天皇は一見生まれ・門地による地位差別、世襲差別の存在のように見えますが、その世襲の中身は西欧王室のような利権世襲・門地直系独占世襲ではなく預かり世襲・非独占世襲となります。
実際、法制上の天皇・皇族における門地的位置付けは非常に限定的であり、終身利権化や代々に渡る固定的な特権維持が出来ない仕組み、数世代毎に入れ替わるような制度設計になっています。
例えば天皇・皇太子の長男として生まれればその長男は天皇となりますが、わが子に世襲させられるかと言えばそうとは限りません。娘だけで息子がいない場合は世襲させられませんし、長男であっても妊娠時崩御のような場合は世襲させられない規定になっています。
天皇の長男でも天皇になれない妊娠時崩御 家督・相続物でない証左
非常に制限の大きい世襲規定であり、門地利権・直系の独占物という形で私物化が出来るような特権的な地位・世襲とはなっていません。
短期ではなく中期:数世代で見るとやがて他家に譲る形になる地位・世襲となります。
(また女性皇族に関しても民間人との結婚により皇族の立場を離れる形での規定となっていて、立場を世襲で終身利権化出来る規定にはなっていません)
この意味において天皇・皇室における世襲規定は、憲法14条の法の下の平等、門地差別禁止の理念と根本矛盾するものではなく、中長期で(輪廻輪番的に)天皇・皇族・国民がそれぞれの立場で役割を担うという高度な、和的な位置付けとなります。
こうした抑制的で和的な位置付けだからこそ、憲法1条において「象徴」「国民の総意に基く」と規定されるのであって、天皇・皇族を安易に憲法の例外・飛び地論などで捉えるのは不相当です。
こうした捉えでは、”飛び地”を言い訳にしての門地利権化・直系利権化=女性天皇(娘継承)、女性宮家・皇女制、養子などの論を助長しかねません。
*
皇位継承における世襲、皇室典範の根本理念は、典範1条に規定される通り「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」(民間にある神武男系男子は千万単位)という形になります。これは憲法1条、2条(世襲により継承、皇室典範で定める)と整合し、皇位継承者の不足・不在により天皇が不在・空位になることはないという規定です。
一方皇室典範においては、第2条で「皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える」との形で「皇統に属する男系の男子」でありつつ「皇族」という条件を規定しています。
そして、15条で「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」と規定していて、皇族が全員いなくなった場合、皇族に男系男子の継承者がいない場合に対処出来る、天皇の空位を回避する規定は設けられていません。
すなわち、憲法1条、2条と、皇室典範1条、2条は整合しているのに、典範15条がそれらに矛盾し不整合で危機における皇室再建の重大な障害になっているという状況となります。
あらためて、民間にある「皇統に属する男系の男子」を皇族に組み入れる規定を整備(皇室典範15条等を改正)することが必要となります。
そもそも皇室典範の施行(1947年 昭和22年5月3日)に際しては、明治の皇室典範の効力がなくなることにより皇族身分の根拠を失う=一般国民となる皇族(筆頭は明仁皇太子)の皇族身分を維持する意味で、皇室典範の「附則」によって”この法律による皇族とする”旨規定されています。
皇室典範 附則
② 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
このことからも明らかなように、そもそも天皇・皇族自体が日本国民であり、日本国民の中から初代神武天皇との繋がり、建国の和への原点回帰性により「皇統に属する男系の男子」の立場で皇族となり、皇位継承順に従い天皇となるというのが日本の皇位継承システム、憲法・皇室典範の根本となります。
日本の国民の中から門地=神武天皇からの繋がり:皇統に属する男系の男子により皇族となり、天皇となりますが、この世襲は非常に限定的な「制限世襲」であり、皇位・皇族身分は門地特権・直系利権として永続化は出来ないようになっていて、数世代毎に天意に基き入れ替わる制度設計になっています=皇位は預かりもの。
この意味で、天皇・皇族の身分は永続的な門地特権ではなく生まれ差別・人間差別・門地差別禁止の理念と根本矛盾しないもの、「預かり世襲」として捉えられます。
こうした制限世襲・預かり世襲による皇位継承・天皇存在・皇族身分だからこそ、和・君民共治の理念にも整合・体現するものとして憲法1条で「象徴」「国民の総意に基く」と高尚に規定されることとなります。
これこそが、憲法1条、2条と14条の整合、”飛び地”などではなく生まれ差別・門地差別禁止と根本矛盾しない世襲・象徴・天皇・皇族・皇位継承の在り方となります。
実際の皇籍への組み入れにおいては、神武一系の正統継承者という位置付け・由来に鑑み、現行法制:皇室典範の条文に則って養子などではなく直接的な組み入れとすることが重要です。
(この意味で「護る会」の提言は伝統、法制を損ねるものとなります
旧宮家の子孫の方々に非常に無礼な「護る会」の提言 養子前提など不見識も甚だしく)
もちろん女性皇族との婚姻も(婿養子に限らず、それ以外の形でも)無用です。むしろ内親王が結婚後も皇族身分を確保するために男系男子・皇位継承者を便利な道具的に扱うことを禁じる意味で婚姻は禁忌事項、皇室会議では不相当の議決が必要という議論、国民的な再確認が重要と捉えます。
また、皇位継承順を割り振るに際して、復帰一代目は除外して次に生まれた者から順位を付けるなどという姑息、弥縫策は避け、組み入れた当人を正統継承者として順位付けすることが重要となります。
(第119代光格即位における婚姻に絡めての一代飛ばし、皇位継承者の便利道具扱い、その後の「尊号一件」の教訓を活かし、現在に再現することのないようにしなければなりません)
皇位の由来、継承の正統性は、あくまで神武一系によるものであり、時の天皇、本統との近さではありません。
皇位の私物化、由来の転換を戒め、国民全体で再共有する意味でも、組み入れた当人を正統継承者として位置付けて、皇統バックアップの宮家体制としていくことが重要となります。
*
憲法は歴史、伝統、和を踏まえた形でつくられているもので、私たち国民の実生活にも大きな影響のあるものとなります。
国、人心が乱れるのも健全に営まれていくのも、憲法を損ねずに理念を実直に具現化していく努力にかかっているものと考えます。
そして今はそれが十分ではない状況と捉えます。
取り返しのつかない状況に至る前に建て直しが必要です。
*
憲法1条、2条に関しては、図表も含めたスライド動画説明を Youtube に登録しました。
ぜひご覧いただきたく。
小中学生のための天皇・皇位継承論 1 後半
・継体天皇 手白香皇女
・推古天皇 蘇我馬子
・光格天皇 後桜町天皇
・明治の皇室典範 高度な昇華
・憲法1条 象徴 国民の総意に基く
・憲法2条 世襲 皇室典範
・旧宮家子孫から皇籍に組み入れ・宮家設立
